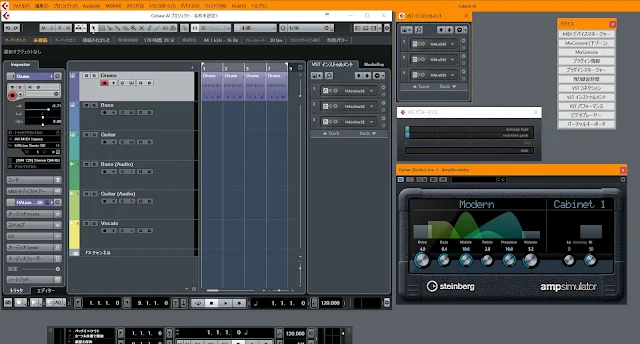お正月に録画しっぱなしだった〔
玉木宏 音楽サスペンス紀行▽ショスタコーヴィチ 死の街を照らした交響曲第7番〕をようやく見ることができました。
~引用
〔
第二次世界大戦のさなか、ドイツ軍に包囲され過酷な状況にあったレニングラードで、ある演奏会が行われた。ショスタコーヴィチが故郷・レニングラードにささげた「交響曲第7番」。飢えや寒さと闘いながら、人々はどのようにして“奇跡のコンサート”を実現したのか?一方、作品の楽譜は密かにマイクロフィルムにおさめられ、遠路アメリカまで運ばれた。ソビエトとアメリカの大国同士が音楽で手を結んだ、驚くべき政治的背景とは?〕~ここまで
ショスタコービッチの作品で私的に特に大好きなのは「祝典序曲」「
5番」「
12番」で
7番は「ちちんぷいぷいのテーマ」ってことくらいしか知らずにその曲の背景を今回初めて知ってびっくり。
1941年9月、ドイツのヒットラーがソ連のスターリンと結んだ不可侵条約を破棄しいきなりレニングラード(サンクトペテルブルグ)へ侵攻。地理的に北はフィンランド・西はフィンランド湾・東はラドガ湖で南から攻め込まれ、完全に孤立してしまう。「レニングラードを地球上から失くしてしまえ!」と宣言されレニングラード包囲戦が900日にわたり行われた。
戦火が激しくなる中、ショスタコービッチは生まれ故郷のレニングラードで作曲を続け、ようやく2楽章を書き終えたところでショスタコービッチはラジオで市民に対しメッセージを流す。それは「私は、新しい交響的作品の最初の2つの楽章を書きあげました。」から始まる祖国や町への愛情を伝えこの交響曲を祖国で演奏を行いたいという内容だったそうです。
ラジオオーケストラはすでに戦地に送られ、怪我人や死者もある状況でこの「7番」は意外な運命を辿っていくこことなります。
レニングラードに大飢饉が襲い、猛烈な飢えと寒さが人々を襲いしかもドイツ軍の火の手が迫ってきます。また弾薬等の資源がつきかけているところでなんとかアメリカの協力が欲しい。
1942年 1月、交響曲第7番がスターリン賞第1席受賞。ロシア共和国功労芸術家の称号を授与することでこの曲への評価を国内で高めたうえで利用することを思いつく。
アメリカ大統領のルーズベルトはドイツの支配を好ましく思わずなんとか社会主義であるソ連へ肩入れをしたと考えたが、自分の任期と当時のアメリカの世相を考えると社会主義に対する反感が強いことからおおっぴらには行えない。
そこでこの「7番」に目を付けた!
「7番」をアメリカで演奏をさせ、世論を動かすことでソ連への支援と自分への評価を高めようと考え楽譜を極秘でマイクロフイルムに収めとんでもないルートでアメリカへ運び入れることに成功した。
さて、誰に演奏をさせるのがBESTか・・・・。
選ばれたのはイタリア出身のトスカニーニ!彼は祖国のファシズム化に抵抗しアメリカへ亡命している。まさに適任!
1942年7月にアメリカで初演され大喝采、以降場末のストリップ小屋のBGMでさえも7番のフレーズを使ったくらいの大人気の曲となるにつれ世論が盛り上がりルーズベルトは再選を重ね、おおっぴらにソ連を支援・・1944年1月にようやく解放。ちなみに
日本の真珠湾奇襲は1941年12月で戦線を南方へ拡大している時期。
そして祖国レニングラードで演奏されたのは1942年8月。まさにドイツとの戦争の真っただ中。もちろん演奏会開催の情報はドイツへも筒抜けでこの日に合わせて総攻撃が予定されていたが、全力攻撃で回避、この「7番」の演奏会の音は前線でも放送されたそうです。
1楽章の小太鼓が刻む一定のリズムにあわせ進軍のテーマが遠くから聞こえてくる。。なんとも陽気な雰囲気のテーマが、回数を繰り返すうちにどんどん変容し、ついにクライマックスを迎えるとなんともおぞましく悲劇的なテーマにかわっていることに誰もが気付きます。戦争のなんとも悲惨で無意味な暴力行為を否定するも逃れることのできない運命に流されていくそんな無力さを思い知ることになります。
こんな感じの流れの番組でした。
玉木宏さんが実際にサンクトペテルブルグで当時の様子を知っている方へのインタビューやその場所をめぐります。
さて、余談ですこしだけ触れましたが、はたしてショスタコービッチの真意はどこにあったのでしょう。
ソ連の社会主義体制に迎合した音楽だけを求められ、批判的と取られたら処刑されるそんな体制での曲作りに嫌気をさしていたのも事実なのでしょう。曲のなかに巧みにメッセージを盛り込み苦しみながらも体制を笑っていたのかもしれません。